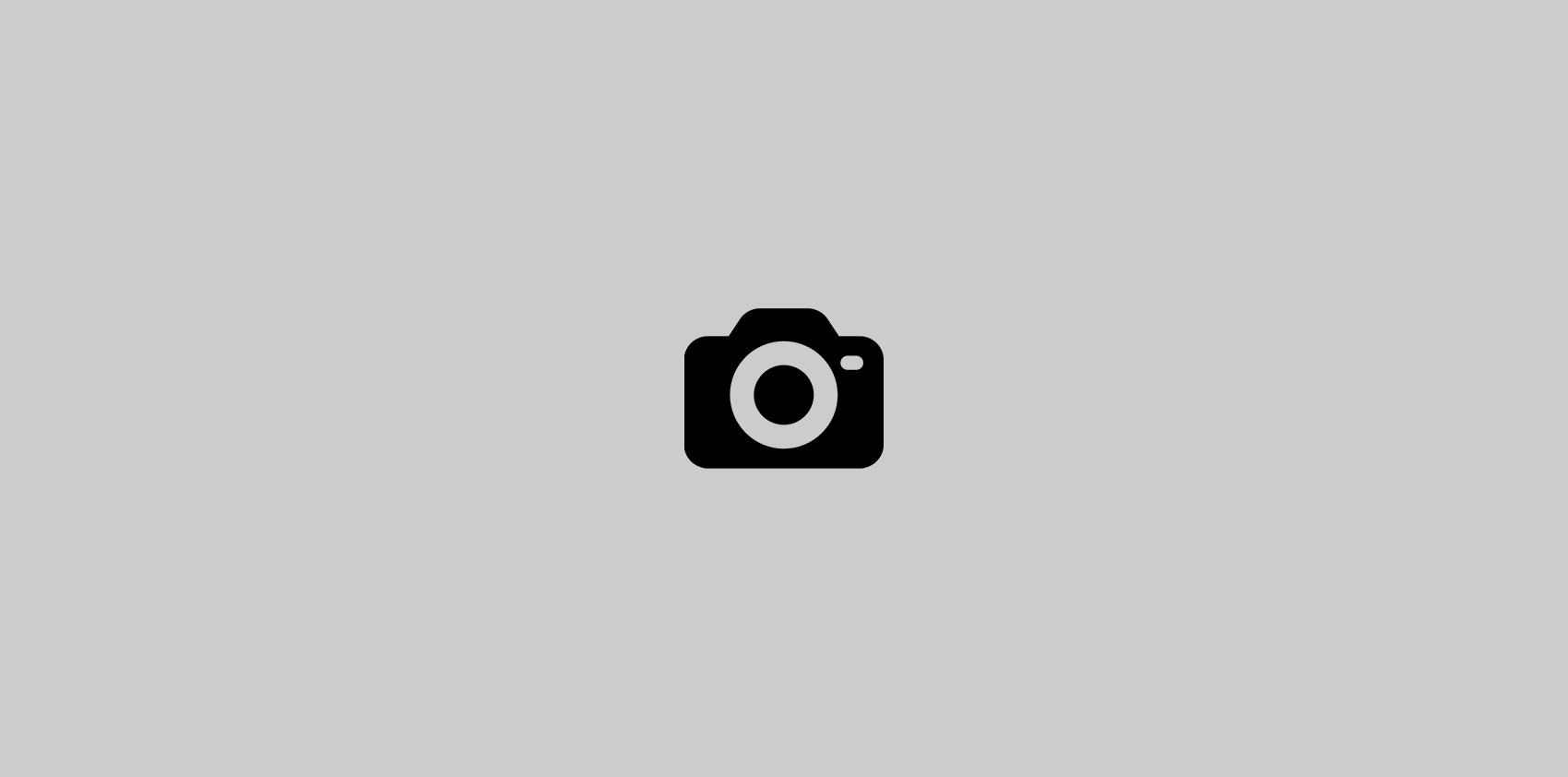ビジョン・ミッション・バリューを導入する意義・メリットとは
「ビジョン」は、ビジョン・ミッション・バリューという3つのうちのひとつであり、企業の存在意義を内外に示すものである、ということをご理解頂けたと思います。では、「ビジョン」を始めとしてミッション・バリューを設定・あるいは見直しをすることで、どのような効果があるのでしょうか?
メリット1(社内向け)社員の企業に対する理解が深まり、生産性や定着率が向上する
ビジョン・ミッション・バリューの作成や見直しは、企業の方向性を社員に明確に示す効果があり、社員のエンゲージメント(従業員の熱意、積極的な関与)向上につながります。「ビジョナリー」という言葉がありますが、実は企業の中でも、未来を見て仕事ができる人材はそう多くありません。しかし、経営者は往々にしてビジョナリーピープルであることが多いのです。そこで経営発信で、会社の未来について、またそこへ向かうために今すべきことを宣言することによって、「この会社に賭けてみよう」「自分もここで力を発揮したい」という機運が社内に醸成されます。
また、「ミッション」の形で行動指針が言語化されることにより、従業員が業務において判断に迷うシーンがあっても、自律的に決断・行動ができるようになります。同じゴールを見つめることによって、「その仕事を通して何を達成するのか」の迷いがなくなり、生産性が向上することでしょう。
メリット2(社外向け)採用の成功率が上がる、就職先として人気が出る
社会人に「転職したい企業」を聞くと、経営理念や経営方針に共感する企業が上位にランクインする傾向があります。どんな事業を行なっているのか、その事業は社会の役に立つのか、等が世の中に伝わることで、「入社したい」と考える人も多くなります。
また、ビジョン・ミッション・バリューへの理解が深い社員が採用活動にあたると、その企業の魅力が応募者に伝わりやすくなります。会社に愛着を持った社員は、外から見ても眩しく映ることでしょう。バリュー(価値観)、カルチャーが社員を通して伝わることで、その企業にフィットした人材を採用しやすくなります。
メリット3(社外向け)その企業に対する社会的な信用が上がり、企業の更なる成長につながる
ビジョン・ミッション・バリューを作成することによる、最も高いメリットがこれではないでしょうか。社会の中で経営者が持っている高い志、社会をより良くしていく覚悟が、これらの宣言によって世の中へと伝わります。それにより、単なる儲け主義・売上だけを目指している企業ではない、社会的責任を担った企業であるという評価を得ることができます。
企業がしっかりとした方針を持っていると認識されると、取引先の経営者や金融機関、ベンチャーキャピタルなどから注目され、支援を受けやすくなります。また、自社の目指す方向に共感する企業からの提携のオファーや、メディアからの取材依頼も増えていきます。結果的に、企業の成長が加速しやすくなります。
メリット4(社外向け)個人投資家からの理解が得られ、株価に良い影響が出る
企業が自社のビジョンやミッションを明確にすることは、取引先だけではなく個人投資家から共感を得られるというメリットもあります。すでに上場している企業や、IPOを目指す企業にとっても大変重要な戦略です。特にBtoBのベンチャー企業などは、あまり知られていない商材を扱っているため、自社の成長性や将来性をアピールするのが難しい場合があります。そこで企業の考え方、ビジョン・ミッション・バリューをしっかりと伝えることで、「革新的な企業である」「視野が広く、賢明な経営をしている」「環境意識が高い」などのイメージを持ってもらうことができます。未来への期待感が醸成できれば、資金調達につながることでしょう。
加えてサステナビリティやSDGsへの取り組みについても、自社のサイトなどで明示することで、より信頼感や安心感を与える企業イメージを築くことができます。
ビジョン・ミッション・バリューの策定方法・進め方
では、ビジョン・ミッション・バリューは具体的にどうやって作るのでしょうか。完成品がモノというより「言葉」であるだけに、作り方のイメージが湧きにくいものだと思います。ここではカラビナが、コンサルティングを通してお手伝いをした中での一般的な流れをご紹介します。
1. 自社現状分析
まず、自社がどのような状況に置かれているかを私たちと共に分析してみましょう。ここでは3CやSWOT分析、各種のワークショップなどを通して、定量&定性的に分析し、自社を客観視します。とはいえ、ビジョンなどの策定は事業戦略の策定とは異なります。もっとも大切なのは、経営者の「意志、想い」です。数字では表せない、自社の中に眠った「志」にこそ私たちは光を当てていきます。
カラビナでは、様々なワークを通してミッション・ビジョン・バリューの原型を探っていきます。
1)経営陣向けワーク
キーマンインタビュー
自社や担当事業の未来、あるべき姿などについてインタビュー
キーマンワーク
・上記の基礎情報を元にしながら、ありたい姿や自社が関わるフィールドでの未来の「機会」と「危機」の整理
・経営陣それぞれのWillや野心のヒアリング
・それらを統合した「未来イメージ」の言語化
などを通して、ビジョンの具体化を行なっています。
2)若手や中堅のキーマンを巻き込むビジョンワーク
「自社を知る」
自社の「いいね」「もったいないね」などの価値観を用いて、社員が感じる自社の可能性と課題を棚卸しする。
ステークホルダーインタビュー
顧客や同業、パートナー、自社のキーマン(社長などの経営陣)へのインタビューを通して自社の強みや弱み、社外からの期待などを把握する。
未来ワーク
多角的に自社の未来の「機会」と「危機」をイメージングし、自社がどのように進むべきかを想像していく。
ありたい姿の見える化
自社ならではの強みや特徴を意識しながら、来る未来に向けて自社のありたい姿やスタンス、自社ならば実現できるであろう世界観を描き出す。
ありたい姿の言語化
これまでのワークの集大成として、ビジョンとなるキーワードや世界観を整理し、クリエィティブな観点から言語化。多くのケースで補完するビジュアルなども併せて開発し、参加していない社員にも“理解できるように”整えていく。
2. ビジョン・ミッション・バリューの言語化
言語化する際に必要なのが、クリエイティブの力です。なぜ、「経営者の想い」そのままではいけないのでしょうか?それは例えば、「座右の銘」を例に考えてみるとよくわかると思います。自分が大切にしている言葉が、なんとなく「普通」だったり、言葉として魅力的でない場合、他人に伝えたくはならないものです。企業のビジョン・ミッション・バリューは、他人に言いたくなる「座右の銘」のようなもの。社員がついつい唱えたくなる、社外の人が聞いたら憧れる、そんな言葉になっている方が、求心力があるはずです。その時に大切なのは、「経営やビジネスへの理解力」と、「人の心を動かす言葉を作るクリエイティブ」の両方です。この両輪を駆使して、ビジョン・ミッション・バリューの言語化を行います。
3. 社内への浸透施策についてアクション設計(タスク・スケジュールの策定)
ビジョン・ミッション・バリューを作成したら、それを社内にどのように定着させていくかを検討します。コンセプトブックのように本の形にしたり、ビジョンムービーのように、目で見てイメージできる映像にしたり、などが考えられます。また、もっとスピーディーに伝えたい場合は、社内ポータルサイトを使って、経営層からのメッセージという形で届ける方法もあります。M&Aなどで、ビジョンなどの浸透が急務である場合、もっと小さな単位、例えば部署ごとに管理職と社員でビジョンについて対話する会を催すなど、コンパクトに、ただし確実に浸透する方法を実行している企業もあります。優先順位や、期待したい効果に合わせて、アクションを設計しましょう。
4. アクション実行
3で設計したプランの通りに、アクションを実行していきます。
5. 振り返り、定着度の評価
アクションを実行した後、社内にどのようにビジョン・ミッション・バリューが浸透・定着したかを測定しましょう。特に「ミッション」は、社員の行動指針となりますので、それによって社員の行動が変わったか?良い効果が社内にもたらされたかを、定量&定性で計測し検証することが大切です。定性的には、「ビジョンなどの導入後、仕事に対する向き合い方は変わったか?」などのアンケートを取る方法があります。また定量的には、「エンゲージメントサーベイ」などの方法で、従業員と会社の関わりの深さを把握する方法もあります。